ポイントと値引きの違い 〜行動経済学で読み解くプロモーション施策の本質〜
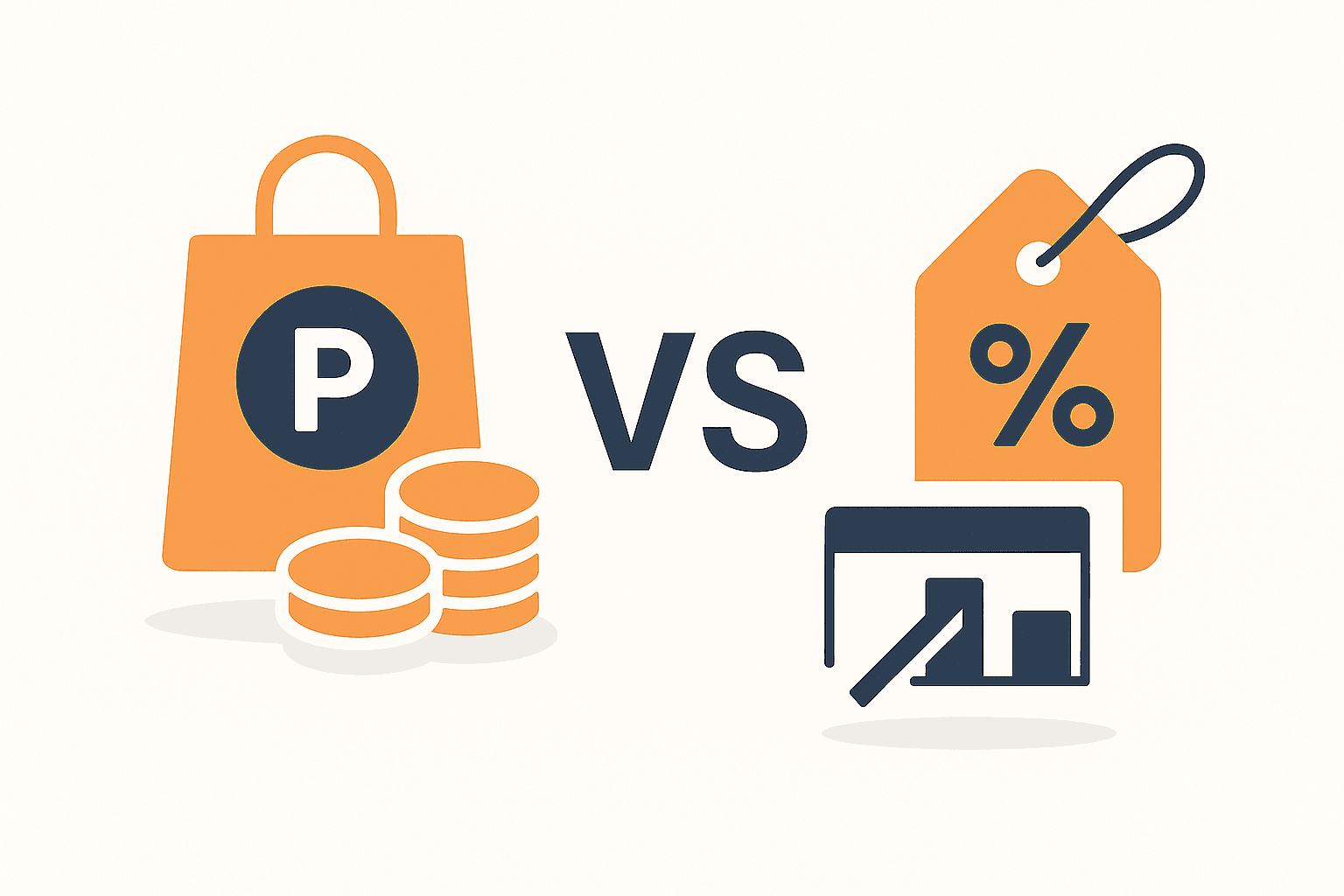
はじめに:同じ“お得”でも、なぜ反応が違うのか?
「本日限定、100円引き!」と「今なら100ポイント進呈!」。
あなたが消費者なら、どちらに魅力を感じるでしょうか? 一見、同じ“お得”であるこの2つの施策。しかし、実際の消費者行動や売上効果を見てみると、その結果は必ずしも一致しません。
なぜ同じ金額でも、値引きとポイントでは反応が異なるのか――そこには、行動経済学や心理的会計(メンタル・アカウンティング)といった、消費者心理の深層が関係しています。
本記事では、実証研究や行動経済学の知見を交えながら、ポイント付与と値引きの違いと、それぞれの効果的な活用法について解説します。
値引きとポイントの違いを心理的に理解する
表面的には「100円の値引き」も「100円相当のポイント」も、消費者にとっては同じ価値を提供しているように思えます。ところが、消費者心理的にはまったく異なる受け止め方がされることが過去の研究結果から明らかになっています。
キーワードとなるのが、リチャード・セイラーによって提唱された「メンタル・アカウンティング(心的会計)」という概念です。これは、消費者が同じ金額であっても、その用途や得られるタイミングに応じて異なる“心の財布”で管理しているという考え方です。たとえば、現金100円の値引きは「支払いの痛みを軽減する」一方で、ポイントは「別の用途で使える未来の報酬」としてポジティブに受け止められやすいのです。
さらに、以下のような違いが指摘されています。
分類 | 値引き | ポイント付与 |
|---|---|---|
タイミング | 即時(レジでの支払いが減る) | 将来的(次回以降の買い物で使用) |
心理効果 | 痛みの軽減 | ご褒美・報酬の獲得 |
認識方法 | 一時的な支出の減少 | 特定の用途で使える“特別なお金”として記憶 |
継続性 | 割引後価格が「通常価格」として認識されてしまう | ポイントプログラムによる囲い込み効果 |
このように、同じ100円でも、消費者は「値引き=損失を防ぐ行動」「ポイント=得をしたという快の感情」として捉える傾向があるのです。
実証研究が示す「逆転現象」
2007年に行われた流通経済研究所の研究における分析では、100円の値引きよりも、100ポイントの付与の方が購買意欲を高めるという結果が複数報告されています。これは、一般的な経済合理性の枠を超えた現象です。
行動経済学ではこれを「Silver Lining Effect(銀の裏地効果)」と呼び、損と得を分けて認識することで、心理的価値が増幅されることを指します。さらに、最新の分析では、値引きの方が即効性はあるものの、参照価格(消費者が“通常価格”と感じる価格)を下げてしまう副作用があると指摘されています。一方、ポイントは参照価格を維持できるため、長期的なブランド価値の維持に効果的とされています。
ケーススタディ:コンビニチェーンのプロモーション比較
ある大手コンビニチェーンでは、以下のようなABテストを実施しました。
- A案:対象商品を10円値引き
- B案:同じ商品に10ポイントを付与
その結果、A案の方が短期的な売上向上に寄与した一方で、B案の方が再来店率の向上や、ポイント利用による他商品の購入につながるクロスセル効果が高いことがわかりました。また、値引きを実施したA案では、プロモーション終了後の売上が急減したのに対し、B案はポイント残高の利用を目的に再訪するユーザーの割合が高く、LTV(顧客生涯価値)を高める結果となりました。
どちらを選ぶべきか? 〜マグニチュード効果の視点〜
近年では「値引きとポイントのどちらが得か?」という議論に対し、「割引率の大きさによって効果が異なる」という新たな知見も注目されています。これはマグニチュード効果(Magnitude Effect)と呼ばれ、以下のような傾向が報告されています。
- 小額(100円以下程度)ならポイント付与の方が効果的
- 高額(数百円以上)なら現金値引きの方が効果的
これは、消費者が「少額の現金は埋もれてしまうが、ポイントなら覚えている」といった心的記憶の違いや、購買の瞬間に得られる満足感の性質によって説明されます。
ポイントの「囲い込み」効果とブランド戦略への影響
ポイントには、単なる金銭的インセンティブ以上の機能があります。それは「囲い込み(ロックイン)効果」です。
自社でのみ利用可能なポイント制度は、他社へのスイッチングを抑制し、自然と継続利用を促します。Amazonや楽天、ユニクロといった企業が長年ポイント施策に注力してきたのも、この「関係の維持」に強く寄与するためです。また、ポイント残高の“可視化”が、消費者の「使わなきゃもったいない」という心理(サンクコスト効果)を引き出し、再訪率・購入頻度の向上につながることも分かっています。
おわりに:目的とタイミングで使い分ける
「ポイントと値引き、どちらが効果的か?」という問いに、唯一の正解はありません。
- 短期的な売上向上を狙うなら値引きが有効。
- 中長期的な顧客育成やブランド強化にはポイントが効果的。
つまり、目的とタイミングに応じたプロモーション設計の“戦略的な使い分け”こそが重要なのです。
行動経済学の視点や実証研究を取り入れたデータドリブンな判断が、マーケティング戦略の成否を左右します。感覚や通念に頼らず、心理的・行動的なメカニズムを理解した上で、最適なプロモーション施策を選択しましょう。
MyStoryはデータサイエンスの専門性をもとにしたデータ解析支援にとどまらず、本コラムで解説したような行動経済学や消費者行動理論の知見を活用した、「ビジネスに寄与する実践的な」マーケティング支援・コンサルティングサービスを提供しております。行動経済学や消費者行動理論を取り入れたマーケティング戦略を立案したい企業様・ご担当者の方はぜひ気軽にお問い合わせください。
【参考】『Price Decisioning』紹介ページ
『Price Decisioning』説明ページへ移動
【分析事例】ポイントと値引きプロモーションの最適設計
分析事例ページへ移動