機械学習の欠損補完はコレで決まり!アルゴリズム×ビジネス理解を融合したデータ前処理の極意
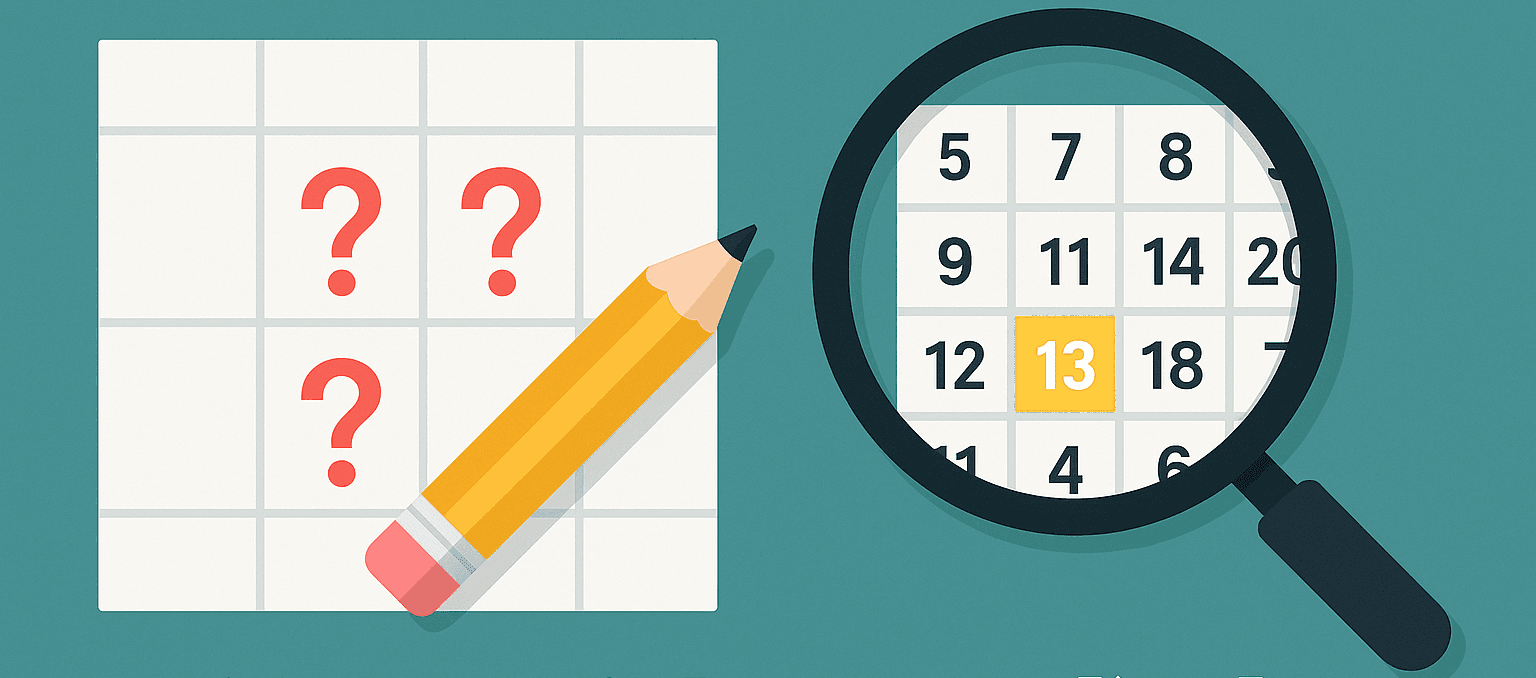
本コラムでは、データ分析や機械学習モデル作成の際に直面する「欠損データの扱い」をテーマに、MyStory社員が普段どんな考え方・手順で欠損を補完しているのかをまとめます。一部、統計学の専門的な内容も含みますが、これまで当社が数多くのデータ分析案件を扱った際の知見や、実務で本当に困るポイントにフォーカスして、可能な限りわかりやすくお伝えします。
機械学習における欠損補完・欠損処理は、単なる前処理ではなく、「どんな現実をデータとして残すか」を決める重要なデータ前処理の工程です。
欠損値は「ノイズ」ではなく、“現実”そのもの
まず最初に強調したいのは、欠損値(=データが入っていないセル)は、ただの「穴」ではなく、しばしば“意味のあるシグナル”そのもの、だということです。機械学習の欠損補完を考えるうえで、この視点は欠かせません。
たとえば人事データで「研修受講評価」が欠けている人がいたとします。この“欠け”は単なる入力漏れではなく、
- そもそも研修にまだ参加していない新人だから未評価なのか
- 休職や長期不在で評価機会そのものがなかったのか
- 上司評価自体が遅延している部署だから記録されていないのか
など、組織上の文脈と結びついていることがよくあります。
この違いを無視して機械的に「平均値で埋めておきました」「0で埋めました」としてしまうと、分析データは一見きれいに揃いますが、現場から見ると「ぜんぜん実態と違う」ものになるリスクが極めて高いのです。だからこそ、機械学習の欠損処理は“集計前の地味な下ごしらえ”ではなく、“分析の成否を左右するコア工程”です。MyStoryではそこをかなり重く扱います。
欠損には複数のパターンがある
欠損といっても全部同じではありません。代表的には次の3タイプがあります。機械学習のデータ前処理では、まずこの違いを押さえることが重要です。
- ① MCAR(Missing Completely At Random)
「完全にランダムに欠けている」状態です。
(例:一部の回答行が通信エラーで落ちた、担当者が手入力で何件か抜かした、など。)
データの持ち主の属性や値とは関係なく、たまたま抜けたパターン。
→ MCARであれば、欠損を持つレコードを除外しても、統計的なバイアスは比較的小さく済むことがあります。
- ② MAR(Missing At Random)
「観測済みの別の情報に依存して欠けている」状態です。
(例:若手社員はまだ評価会議を経ていないので評価スコアが未入力、専門職は自由裁量労働なので残業時間の記録が欠けやすい、など。)
→ “完全なランダム”ではないので、単純に落とす・平均で埋めると特定のグループが体系的に薄まったり歪んだりします。現場の意思決定を誤らせる典型パターンです。
- ③ NMAR(Not Missing At Random)
「欠けていること自体が、その人の値と結びついている」状態です。
(例:自己評価の低い人ほどアンケートに答えない/離職意向が高い人ほどエンゲージメント調査に無回答、など。)
→ これは最も扱いが難しいタイプで、単純補完はほぼNG。統計モデルの仮定を工夫したり、現場ヒアリングから“なぜ欠けているのか”を解釈して扱う必要があります。
この3つを見極めずに「欠損しているから0で埋めよう」「平均値補完でいいよね」とやると、MARやNMARの欠損を“都合よく丸めた”だけの分析になります。つまり、解くべきは現場の課題なのに、分析の入り口で歪みを入れてしまうことになるわけです。機械学習の欠損処理を設計するときは、ここを丁寧に見極める必要があります。
よくある“ダメな欠損処理”
- 平均値で埋める
部署別の評価スコアが欠けていた社員に、部署平均のスコアをそのまま代入する──これは一見合理的ですが「その人の評価が高い/低いから欠けている」場合(=NMAR)には完全に逆効果です。平均で埋めることで、評価分布を人工的に中央へ押しつけ、優秀層・リスク層のシグナルを消します。
- 0で埋める
出社日数や残業時間など数量データでありがちな処理です。たとえば「残業時間の記録が欠けている人は0時間とみなす」と置換すると、“記録されていないだけでかなり働いている人”が、分析上は「超ホワイト勤務」に見えてしまうことがあります。人事のアラート設計で誤作動します。
- 欠損行ごと捨てる
アンケート回答で1問でも未回答がある人を分析対象から外す処理もよくあります。これをやると「忙しすぎて回答しきれなかった人」「不満が高くて回答したくない人」などが丸ごと消え、残った“ヒマで従順な層”だけで平均値を語ることになりがちです。組織改善の緊急度を過小評価してしまう危険があります。
この3つのやり方は、レポートの見た目はきれいでも「経営が本当に知りたい状態」を隠してしまうことが多いです。機械学習の欠損補完・欠損処理を行う際には、まず避けたいNGパターンだといえます。
統計的な欠損補完アプローチ
もちろん、欠損処理は闇雲な職人芸だけでやれ、という話ではありません。機械学習のデータ前処理として、統計学にはしっかりしたメソッドが蓄積されています。その代表例が以下の2つです。
EMアルゴリズム(期待値最大化法)
EM(Expectation-Maximization)は、欠損を含むデータの「ありそうな分布(確率モデル)」を推定し、その分布から欠損値の期待値を推定していく手法です。ざっくりいうと、
- いま観測できているデータから分布を推定する
- その分布を使って欠損部分を推測(期待値で“仮埋め”)
- その“仮埋め後”のデータでもう一度分布を更新
……というサイクルを収束するまで回します。
ポイントは、「他の列との関係性」を踏まえて埋めること。単純平均よりも、年齢・部署・職種・勤続年数・評価ランクなど、関連する特徴量を同時に使えるため、“その人らしい”補完値に近づけやすくなります。
多重代入法(Multiple Imputation)
EMに近い発想ですが、「1回だけ埋めて終わり」ではなく“複数パターンの埋め方”をつくって分析し、その結果を統合します。メリットは2つあります。
- 欠損補完自体の不確実性も、最終的な推定結果の誤差にきちんと反映できる
- 「たまたまこう埋めたから、たまたまこうなった」という一発勝負の偏りを避けられる
人事データのように、性別・年齢層・職位・勤務地などが複雑に絡んで欠損が発生している場合、多重代入法はかなり有効です。特定セグメントだけ系統的に欠損している(=MAR型の欠損)ケースでも、歪みを緩和できます。
「アルゴリズムだけ」では実務ではNGな理由
ここからが、MyStoryがビジネスデータ分析の実務において一番大事にしているところです。統計的な手法(EMアルゴリズムや多重代入法)は強力ですが、万能ではありません。特に人事領域では「なぜ欠けているのか」に制度・運用・タイミングなどのビジネスロジックが深く関わります。
たとえば、私たちが過去に行った人事データの分析では、以下のようなことがありました。
- “汎用スキル”のアンケート回答が欠けている社員は、4〜5月入社直後の新入社員に集中していた
→ これは「まだ正式な面談や評価プロセスを経ていないから未記入」という業務上の理由が明らか。 - “業務経験”の設問が欠けている社員は、特定の専門職カテゴリに偏っていた
→ その職群はジョブ内容が特殊で、共通フォーマットの業務リストがそもそも当てはまりづらく、回答時点では職務記述が固まっていなかった。 - “出向/出向予定”などのキャリア履歴情報は、休職・長期出張・人事異動タイミングと絡んで抜けがち
→ つまり欠損は「管理プロセスの遅延」や「制度の例外運用」の痕跡でもある。
ここで「機械的に平均値で埋める」「回帰モデルで推定して代入する」だけだと、むしろ現実から遠ざかります。なぜならこの欠損は“まだ評価対象になっていない人”や“制度上フォーマット外の人”という、まさに経営が知りたい層の特徴そのものだから。
だからMyStoryでは、統計アルゴリズムによる補完の前に・あるいは並行して、次のようなロジックベースの補完方針を整理します。
- 「入社1〜2か月以内の新入社員」は、まだ評価プロセスが未実施であることが制度的にほぼ確定している
→ 該当層だけは“前年の新入社員の平均値”で一括補完(=この場合、欠損は「低いから書いてない」ではなく「まだ機会がない」なので、バイアスを作りにくい) - 「専門職A職群の“業務経験”項目」は、共通フォームが制度的にフィットしていなかった
→ 同じA職群内での平均・典型パターンを使って補完(=他職群の平均で埋めると、A職群だけ異様に“凡庸”に見えてしまい、スキルマップの設計が狂う) - 「長期不在中で評価が未入力の管理職」は、当該期間は“評価をつけない”という運用ルールになっている
→ その期間だけ扱いを『未評価扱い』としてダミー化し、数値で無理に埋めない(=無理に数値を埋めると不当にマイナス/プラス評価になる)
これらは単なる思いつきではなく、「どの属性×どの期間×どの制度で欠けているか」をクロス集計して、欠損の発生メカニズムを徹底的に洗い出すところから設計します。この工程こそが、単にアルゴリズムや技術力に長けているだけでなく、ビジネス力や人間の行動科学を強みにしているMyStoryの価値となります。
MyStoryの基本スタンス:アルゴリズム × ロジック
まとめると、MyStoryは機械学習の欠損補完・欠損処理を次のような流れで進めます。
- 欠損の構造を診断する
✓ MCAR / MAR / NMAR どの欠損タイプが支配的か
✓ 欠損が特定部署・特定職位・特定の人事イベント(異動、出向、休職、入社直後など)と結びついていないかを確認する
✓ 「欠損している人は誰か?」を可視化することで、そもそも経営が注目すべき人たちが浮かぶことすらある
- ロジックベースでの補完ルールを定義する
✓ 制度・運用・時期に由来する“必然の欠損”には、業務ロジックに沿った埋め方を明文化する
✓ 「平均で埋めるのが妥当なグループ」「数値では埋めず別ラベル(未評価)として扱うべきグループ」を切り分ける
- 統計的補完手法を適用する(EM アルゴリズム/ 多重代入法など)
✓ 上記ルールでまだ埋まりきらない欠損については、EMアルゴリズムや多重代入で“その人らしい”値を推定
✓ その際、推定の不確実性もレポートし、意思決定側が過信しないようにする
- 意思決定での使い方まで設計する
✓ 経営会議や人事会議で使う指標に、どの程度の信頼性とバイアスが残っているかを明示
✓ 「この指標は新人にはまだ安定していない」「休職者は別扱いで見るべき」といった注意喚起も併せてお渡しする
この“アルゴリズム×ロジック”の組み合わせを行わないと、きれいなダッシュボードができたとしても、結局「現場の肌感とズレていて誰も使わない」という悲しい結末になりがちです。逆に、このプロセスを踏んでいれば、経営や人事部門が「この数値はどの前提で推定されたのか?」という説明責任に耐えられるようになります。
まとめ:欠損処理は「分析の下準備」ではなく「経営判断の土台」
✓ 欠損にはMCAR / MAR / NMARという欠損タイプがあり、ただ埋めればいいものではない
✓ 平均値で埋める/0で埋める/とりあえず削除する、といった安易なやり方は、組織にとって一番重要なシグナルを消してしまう
✓ EMアルゴリズムや多重代入法のような統計的メソッドを使えば、より妥当な推定値を得られる
✓ ただし実務では、制度・運用起因の欠損を理解したうえで“ロジックで埋める/埋めない”を設計することが欠かせない
✓ その2つを組み合わせ、分析に耐えるデータをつくってこそ、現場のアクションプランに落とせる
MyStoryの役割は、単に「欠損を埋める作業代行」ではありません。「欠損が示している組織の構造」「そこからにじむリスクや機会」「経営がどこを見にいくべきか」を一緒に発掘し、意思決定に耐えるデータ基盤をつくることです。これが、私たちが“欠損処理”と呼んでいる仕事の中身です。
【参考】MyStoryの『データ利活用支援』サービス
『データ利活用支援』サービスへ移動