バリューベースドプライシング:支払意思額から考える新しい価格戦略
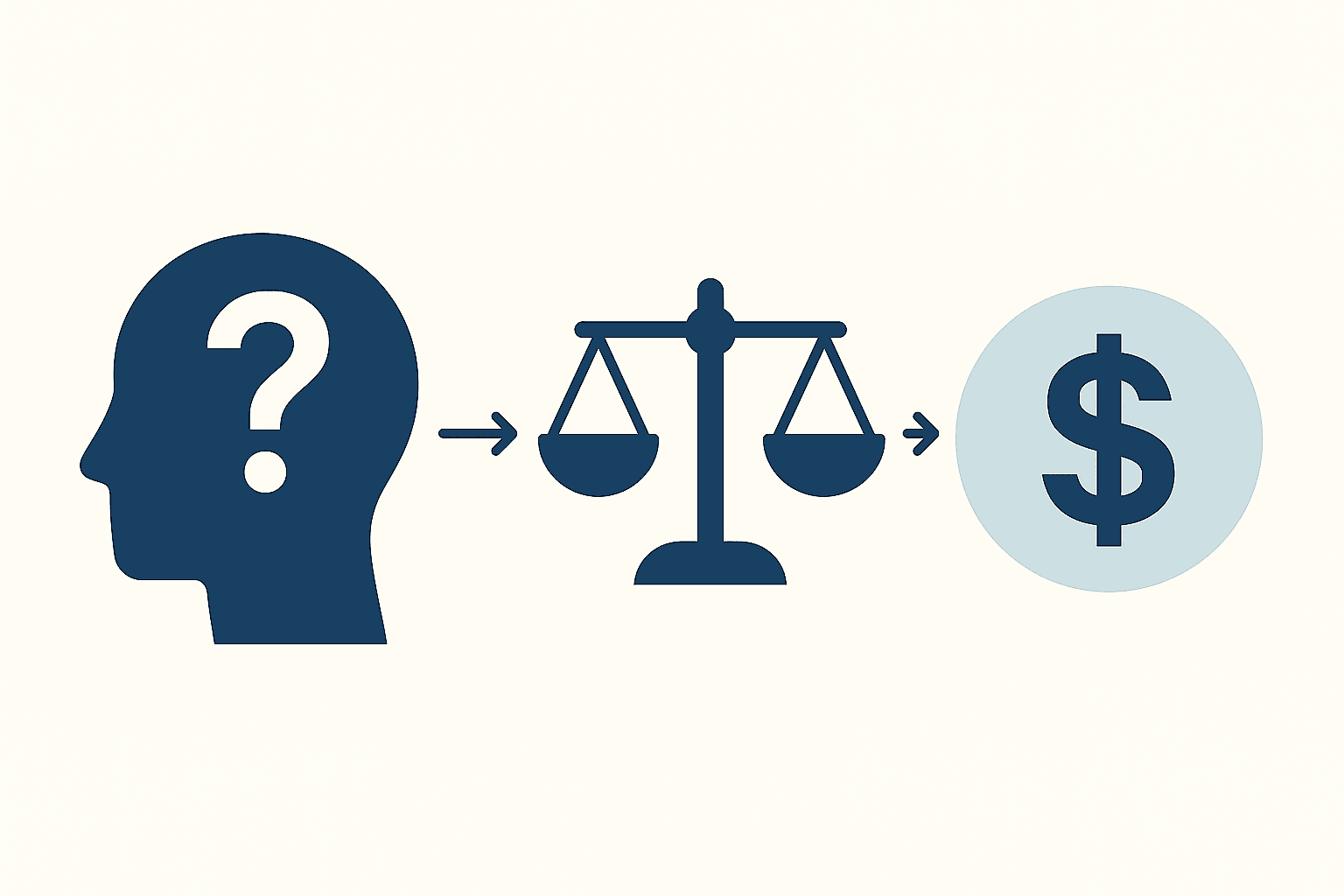
はじめに: 顧客が「価値あり」と思う価格とは? 〜支払意思額の重要性〜
バリューベースドプライシング(Value-Based Pricing)の中核にあるのが、顧客の支払意思額(WTP)です。これは、顧客が商品やサービスに対して「この価格なら購入してもよい」と感じる最大金額を指します。従来のコストプラス型や競合ベンチマーク型の価格戦略と異なり、WTPを基に価格を設定することで、より高いマージンの獲得や、価格を通じた価値訴求が可能になります。
例えば、同じ機能を持つ2つの製品であっても、ブランド力、アフターサポート、導入の容易さといった付加価値が異なれば、WTPも大きく変わります。したがって、製品の持つ価値を構造化し、それぞれの価値がWTPに与える影響を把握することが、適正価格の設計には不可欠です。
コンジョイント分析で「価格に対する効用」を定量化する
支払意思額を把握するための代表的な手法が「コンジョイント分析」です。これは、製品やサービスの構成要素(属性)を変化させた複数の選択肢を顧客に提示し、どの組み合わせが選ばれるかを通じて、各属性の効用(=価値)を数値化するものです。
例えば、クラウド型の業務ソフトに関する調査では、「初期費用」「月額料金」「サポート体制」「カスタマイズ性」などが属性となります。それぞれの水準(たとえば月額3,000円 vs 5,000円)に対して、どれほど顧客が重視しているかを効用として推定し、最もWTPが高まる構成と価格帯を見出すことができます。
この効用値から「仮想的な市場反応」をシミュレーションすることも可能であり、新製品投入時の価格戦略、既存サービスのリニューアル設計にも応用されています。
効用に基づく価格設計の考え方
「効用(Utility)」とは、顧客が商品やサービスから得られる満足度や価値の尺度です。バリューベースドプライシングでは、価格を支払うことによって失われる効用(負の効用)と、商品から得られる効用(正の効用)との差分がゼロになる価格、すなわち「中立点(Indifference Point)」を探ります。
この考え方に基づくと、ある価格以上では購入意欲が急速に下がる「限界価格」や、価格に敏感に反応する「効用変化の勾配(価格弾力性)」を把握することも可能になります。特にSaaSなどサブスクリプション型のビジネスでは、長期契約と短期契約に対する効用の違いを意識したプラン設計が収益に大きな影響を与えます。
また、効用の総量が顧客の期待を下回る場合、価格がどれだけ安くても満足度は得られません。これは単なるディスカウント戦略では顧客ロイヤルティを築けないことを示しており、価値の設計と伝達が不可欠であることを意味しています。
顧客価値の可視化がもたらす戦略的示唆
支払意思額と効用構造を定量的に可視化することで、企業は価格設定にとどまらない多くの戦略的示唆を得ることができます。
- 価格帯ごとのターゲットセグメントの明確化
- サービス構成の最適化(バンドル vs アンバンドル)
- 差別化戦略の根拠となる価値訴求ポイントの明確化
たとえば、「サポートが充実しているから高くても選ばれる」といった直感的判断を、コンジョイント分析によって定量的に裏付けられれば、営業現場や広告展開におけるメッセージも一貫性を持って強化できます。
バリューベースドプライシング導入への第一歩
価値ベースの価格設計は、単なる価格の見直しではなく、顧客視点から事業の在り方そのものを再設計する営みでもあります。
MyStoryが提供する「Price Decisioning」は、バリューベースドプライシングをはじめとする最新の価格戦略を、実データに基づいて構築・実装するコンサルティングサービスです。コンジョイント分析やWTP調査の設計支援、AIによる効用予測モデルの構築、社内の価格戦略体制の整備まで、貴社に最適な価格設計をワンストップでサポートします。
【参考】『Price Decisioning』紹介ページ
『Price Decisioning』説明ページへ移動
価値を正しく伝え、利益につなげたいすべての企業様に、戦略的な価格設計の実践をおすすめします。