「どちらでもない」が増える理由と対策――中間選択のリスクと向き合う
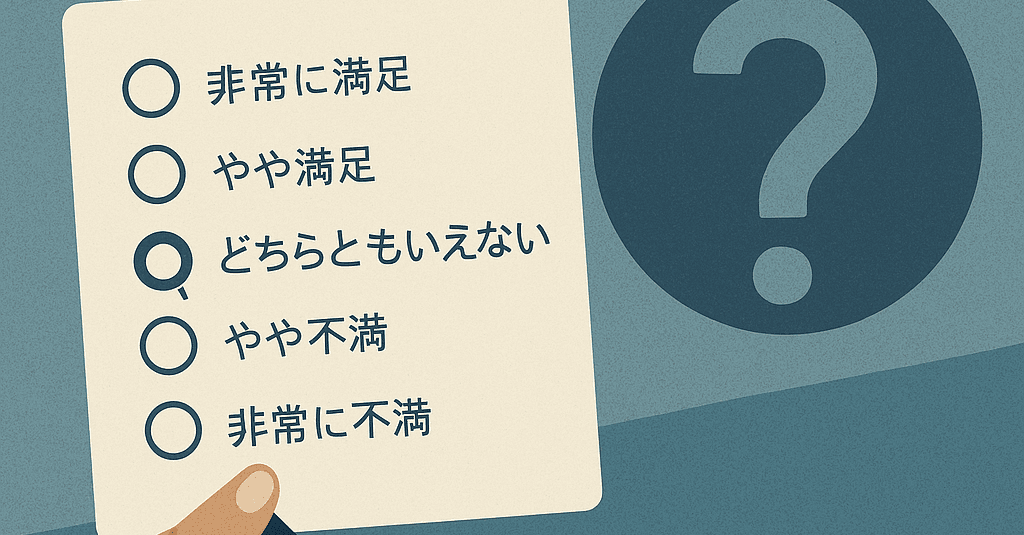
5件法などのリッカート尺度を使ったアンケートでは、「非常にそう思う」「ややそう思う」「どちらともいえない」「あまりそう思わない」「全くそう思わない」のように、中間選択肢が用意されることがよくあります。本来この中間選択肢は「賛成でも反対でもない中立の態度」や「判断が難しい」という正直な立ち位置を表すものとして設計されています。ただ、現実のデータを見ると、中間選択肢が「安全な逃げ道」として乱用されることがあります。
たとえば、
- よくわからないからとりあえず中間選択肢
- 考えるのが面倒だから中間選択肢
- 本音はあるけど会社にバレそうで怖いから中間選択肢(従業員サーベイでありがち)
という“とりあえずの回答”が混ざってしまいます。これは、調査対象者の本当の態度とは別の理由で中間選択肢が選ばれてしまっている、ということです。
この「なんとなく中間選択肢」がたくさん混ざると何が起きるかというと、
- 平均値がどの設問でも真ん中寄りに集まってきて差がつかない
- 部署間・年代間の差が小さく見えてしまう
- 会社として「課題なし」と誤解しやすくなる
特に従業員サーベイだと、経営は「どの項目もそこそこ満足されているから大丈夫そうだね」と読みがちになります。実際には“満足だから中間選択肢”ではなく“無難だから中間選択肢”かもしれないのに、です。つまり中間選択は、組織のリスクや不満のシグナルを平らにしてしまうノイズにもなりうるのです。これは、健康状態・エンゲージメント・離職意向といったセンシティブな領域ほど問題になります。
そもそも、なぜ人は「中間選択肢」を選びやすくなるのか?
これは心理的なメカニズムと、調査票の構造上のメカニズムの両方があります。
- (1) 認知コストを下げたいから(= 最小限化)
人は、アンケートにまじめに答えようとすると、質問文を読み、状況を思い出し、自分の態度を整理し、選択肢を比べてからクリックします。これは地味に負荷が高い作業です。そこで、一問一問しっかり考える代わりに「そこそこ無難なカテゴリで手を打つ」ショートカット戦略をとることがあります。これを調査方法論では「最小限化」と呼びます。完全に最適な回答ではなく、“それっぽいし怒られなそうだからこれでいいや”と判断してしまう回答行動のことです。
この最小限化の典型パターンのひとつが、中間選択です。考える手間も、角が立つリスクも、ほぼゼロで済むからです。
- (2) 疲れるとさらに真ん中を多用する
興味深いのは、「中間選択肢を選ぶ率」はアンケートの後ろに行くほど上がるという現象が確認されていることです。大量の設問に答えていくと、人はだんだん疲れてきますよね。その疲労が、さきほどの“最小限化”を強く促進する。結果として、後半の設問ほど「どちらともいえない」が急に増える、というパターンが実験的に示されています。
要するに
-冒頭はちゃんと考えて答えてくれている
-中盤から「あーはいはい、だいたいこんな感じね」と流し始める
-終盤は「中間選択肢・中間選択肢・中間選択肢」で急にフラットになる
この現象は、実際のアンケート調査において頻繁に起きます。この“後半ほど中間選択肢が増える”という傾向は、性格特性尺度や職場調査などでも観測されていて、「後半の設問のスコア分布が不自然に中央へ寄る/ばらつきが急に小さくなる」という形で現れます。
- 社内調査は「安全な回答」として中間選択肢を使いやすい
さらに従業員サーベイでは、会社に文句を言いすぎるのも怖い、かといって「大満足」と書くほどでもない…という心理から、“角が立たない回答”としても中間選択肢が濫用されます。これはデータ品質の問題であると同時に、組織文化の問題でもあります。つまり、「安心して本音を言えない環境」は、統計的にも“真ん中だらけのデータ”として可視化されることがあるんです。
中間選択の“ノイズ”をどう扱えばいいのか
MyStoryの『リサーチアドバイザー』サービスでは、中間選択は「悪いから禁止するもの」ではなく、「データを読むときに必ず分離して考えるべき信号」と捉えます。具体的には次のようなアプローチをとります。
(1) 設問設計の段階でコントロールする
- 真ん中をあえて置くのか、置かないのかを戦略的に決める
例えば「会社への信頼」「上司への満足度」のように、経営に直結する質問では中間を置くべきかどうかは慎重に検討します。中立というより“回答回避”として選ばれるリスクが極端に高いからです。一方、「制度の理解度」や「ツールの使いやすさ」のような、事実認識に近い項目では“どちらでもない”は本当にあり得るので、中間カテゴリを残したほうが自然な場合もあります。 - 後半にクリティカルな質問を置かない
さきほど触れたように、アンケートの後半ほど中間選択が増える=回答が雑になりやすいという傾向があります。なので「本音を一番知りたい項目」は前半に置く、という単純だけど効く工夫を入れます。逆に、後半は“事実確認系”や“属性・背景”など、比較的淡々と答えられるものに寄せ、疲労による歪みを抑えます。 - 設問ブロックを分割・休憩を入れる
長いアンケートを1本のかたまりとして提示すると、後半に行くほど中間選択が増える傾向が強くなります。質問群を2つに分ける、ページを分けて“次へ”を押させるなど、心理的なリセットを設けると、中間連打の増加をある程度抑えられるという知見があります。MyStoryでは従業員サーベイでも「前半=職場環境」「後半=キャリアと離職意向」といったかたまり方ではなく、逆に意図的にミックスして並べることもあります。特定ブロックだけ中間だらけになるのを避けるためです。
(2) 集計・解釈の段階で“中間”をそのまま平均に混ぜない
調査結果の読み方も工夫します。
- 「満足」「不満」「どちらともいえない」を別々に見る
部署別・年代別に、“どちらともいえない率”をマッピングします。もし特定部署だけ「満足が高い」でも「不満が低い」でもないのに“どちらともいえない”だけが極端に高いなら、それは“本音が言いにくい”あるいは“部門として方向性が共有されていない”組織文化のサインかもしれません。 - 回答の後半になるほど“どちらともいえない”が跳ね上がっていないかを見る
さきほどの疲労・最小限化の影響が強い場合、ページ後半やアンケート終盤で中間選択率が急に上がります。これは、もはや内容というより調査設計側のノイズなので、その部分を経営判断の主要根拠にしないよう助言します。
ここまでやると、ただ「平均が3.2でした。去年より0.1上がりました」という凡庸なレポートではなく、
✓どの層が本音を避けているのか
✓どの設問が回答回避されがちなのか
✓それがコンプラ不安なのか、疲れなのか、単に質問がわかりにくいのか
まで見えてきます。
(3) 調査後の活用フェーズまでつなぐ
MyStoryが人事・組織開発の現場でよくやるのは、「スコアが高い/低い部署」を並べて終わりではなく、
- “中間ばかりの部署”はマネジメント層へのヒアリング対象にする
- “最初は不満がはっきり出ているのに後半で急に中間だらけになる部署”は、調査設計ではなく心理的安全性の問題かもしれないので、1on1や小規模サーベイで掘り直す
といった、次アクションへのブリッジまで設計することです。これは「アンケートの数字」を“人と組織の意思決定に使える形”に翻訳するプロセスで、まさにリサーチアドバイザーとしての提供価値そのものです。
まとめ:中間選択は「ノイズ」でもあり「サイン」でもある
中間選択は、回答者の本音の中立を示すこともありますが、疲労・面倒・防衛・忖度といった“調査以外の都合”が混じることで、組織の実態を見えにくくしてしまいます。
- その傾向は調査の後半ほど強くなりやすいことが、インターネット調査の実験でも確認されています。
- だから私たちは、設問の並べ方・中間カテゴリの置き方・ブロック構成・集計の仕方・結果の読み下ろし方までを含めて設計し、「社員の本音を意思決定に使えるデータ」として届けることにこだわっています。
もし「うちのサーベイ、全部“ふつう”ばっかりで何もわからないんだよね」という状態なら、それは“社員が何も感じていない”のではなく、“設計と読み方を見直すべきタイミング”かもしれません。MyStoryの『リサーチアドバイザー』サービスは、そこから一緒に入って社員の本音や会社の実態を正しく把握できるサーベイを行えるようにご支援します。
【参考】MyStoryの『リサーチアドバイザー』サービス紹介ページ
『リサーチアドバイザー』サービスへ移動