ピープルアナリティクスVol.1~働き方改革の成果を因果推論で読み解く~
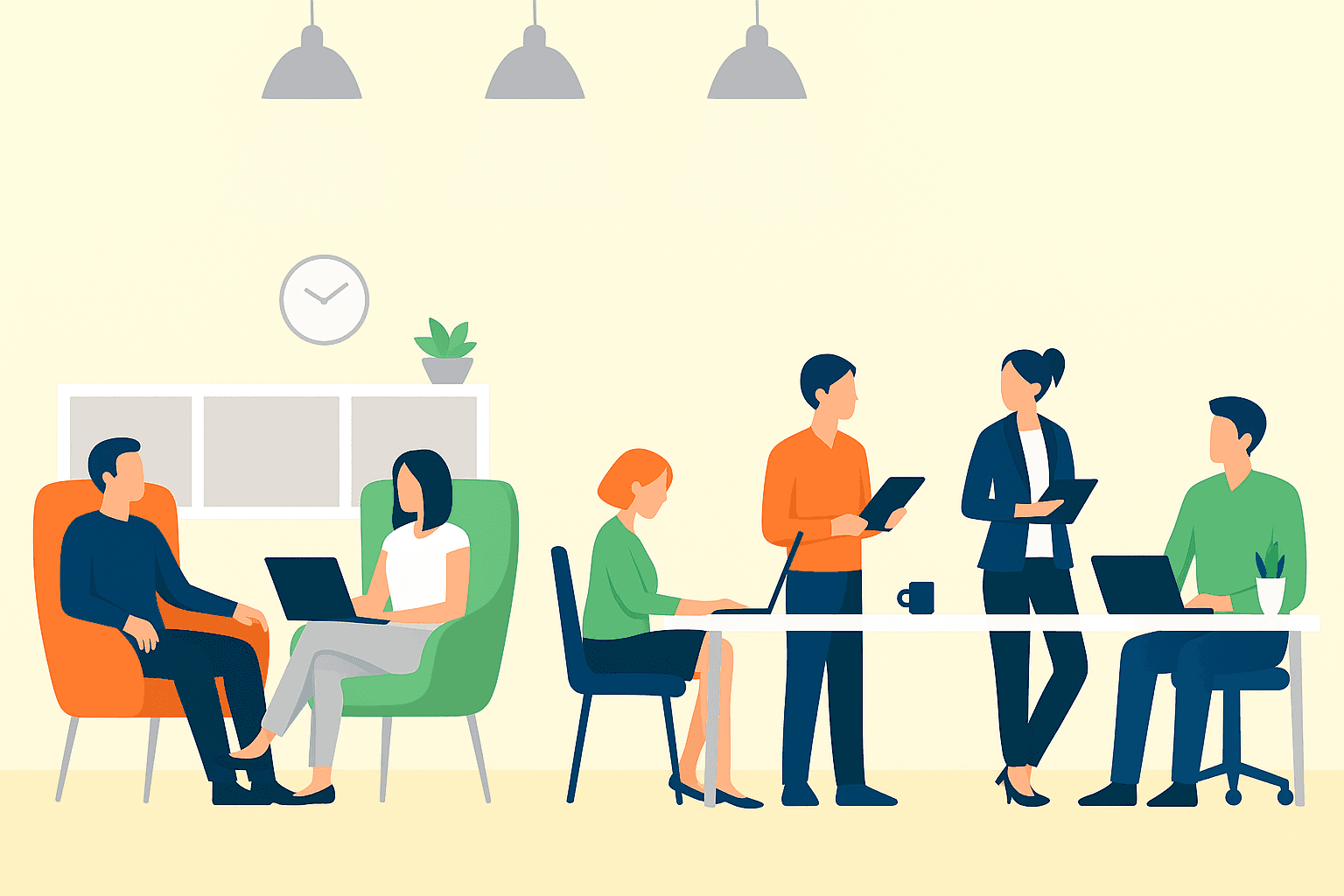
はじめに: 働き方改革の「成果」は本当に証明されたのか?
近年、多くの企業がテレワークや時短勤務などの柔軟な働き方制度を導入していますが、それによって業務効率や従業員満足度が本当に改善されたのかどうかを定量的に示すことは容易ではありません。ここで注目されるのが「ピープルアナリティクス」による因果推論的アプローチです。
従来の「導入前と後で生産性が上がったから制度の効果だ」といった単純な比較では、制度導入の背景にある企業文化やマネジメント能力、制度導入の選抜バイアス(内生性)といった影響を排除できません。働き方改革の効果を科学的に検証するには、因果関係を厳密に捉える統計的アプローチが必要不可欠です。
内生性を乗り越える:マッチング法と回帰不連続デザイン
制度導入の効果を正確に評価するうえで最大の課題は「内生性の問題」です。たとえば「成果を上げそうな従業員ほどテレワークを選ぶ」といった構造がある場合、単純にテレワーク従業員とそうでない従業員の成果を比較しても、その差はテレワークの効果ではなく“もともとの能力差”に起因しているかもしれません。
このような内生性のバイアスを克服するための手法として、「傾向スコアマッチング」や「回帰不連続デザイン(RDD)」が有効です。たとえば一定の評価スコア以上の従業員にのみ制度を適用した場合、そのスコアの境界に近い従業員同士を比較することで、“ランダムな差”として制度の純粋な影響を抽出できます。これは経済学や教育評価の分野で広く活用されてきた設計思想であり、近年では人事領域にも応用が進んでいます。
また、施策導入前後の時系列データを利用する「差の差分析(DID)」や、自然実験と見なせる制度変更時期を利用した分析も、働き方改革の評価において効果的です。
実証例:制度導入とエンゲージメント向上の因果関係
時短制度の導入がエンゲージメントスコアの上昇に与える影響を分析した実証例を以下にて紹介します。
本実証研究においては、単なる平均比較ではなく、マッチング法やRDD、さらには観察データから疑似的に介入効果を推定する因果機械学習手法(Causal Forestなど)も活用されており、学術的な裏付けをもって「働き方改革の成果」を提示しています。
このような分析は、単に「制度を導入した」ことを評価するのではなく、「誰に、どんな条件で、どのような制度が最も効果的か?」といった戦略的示唆を与えてくれる点でも価値があります。
データと実務をつなぐピープルアナリティクスの役割
働き方改革に関連する制度の評価においては、以下のような多様な指標を同時に分析対象とすることが重要です:
- 生産性(売上、業務完了件数など)
- エンゲージメントスコア
- 離職率・定着率
- 上司とのフィードバック回数
- メンタルヘルス関連の相談件数
これらのデータを部門・等級・性別・雇用形態などでセグメント分析し、制度の効果を粒度高く評価することで、経営判断の精度を飛躍的に高めることができます。
MyStoryは働き方改革分析を支援します
働き方改革は、もはや“理念”ではなく“成果”が問われるフェーズに入っています。ピープルアナリティクスを駆使し、制度の影響を定量的に捉えることで、企業の意思決定はより科学的なものとなります。
MyStoryでは、マッチング法やRDD、因果推論手法を用いた制度評価や、働き方データを活用した多面的な分析支援を行っています。働き方改革の成果を可視化し、次の一手を導く分析をお求めの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
【参考】『ピープルアナリティクスサービス』紹介ページ
『ピープルアナリティクスサービス』説明ページへ移動