回答形式間の差異から考えるアンケート設計のポイント
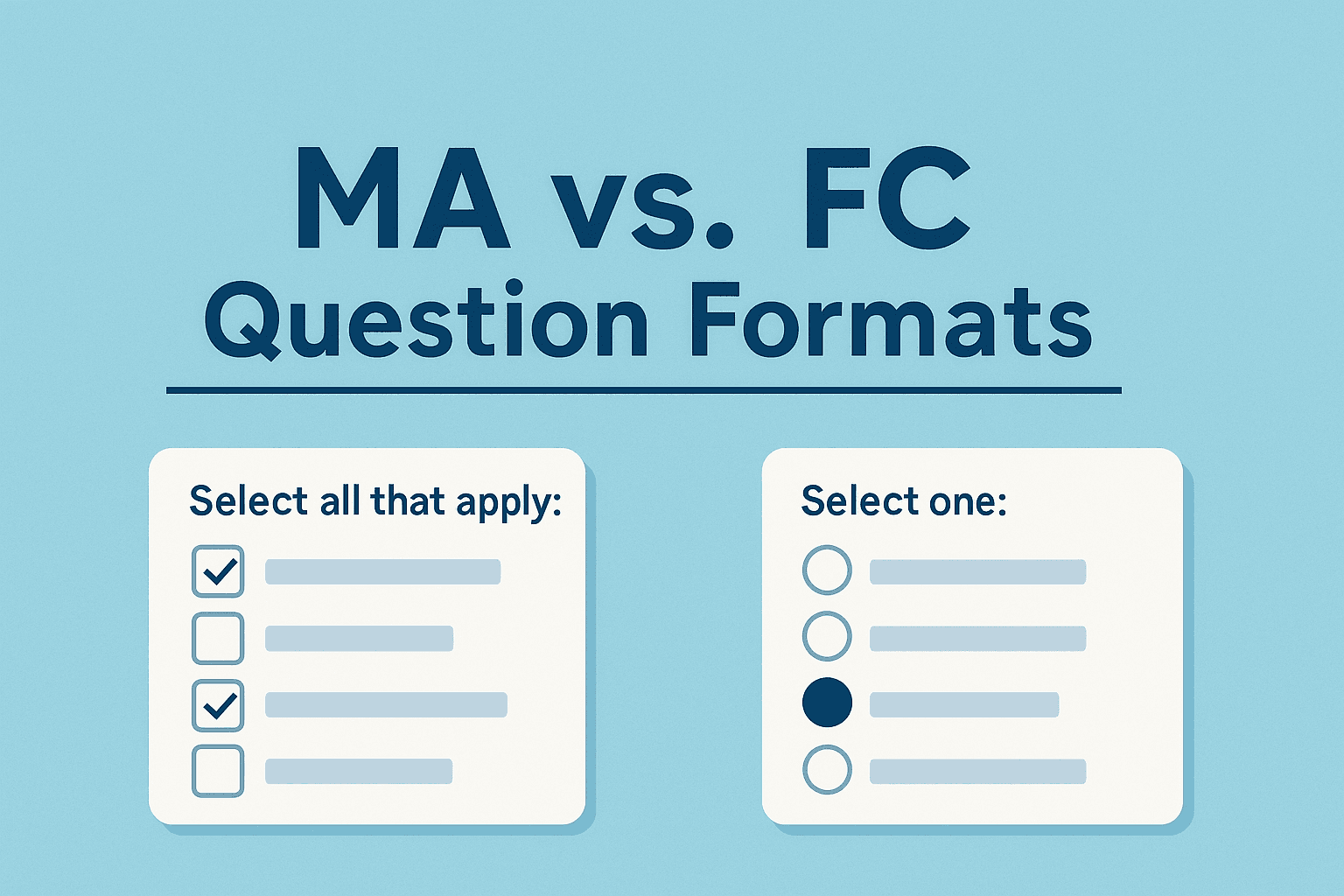
従業員サーベイや顧客アンケートを作るとき、多くの企業が当たり前のように使っている質問があります。
- 「あてはまるものをすべて選んでください(複数選択可)」
実はこの“複数選択可”の聞き方には、大きな落とし穴があります。回答形式を少し変えるだけで、結果が大きく変わってしまうことが、国内外の調査研究で繰り返し指摘されています。MyStoryの『リサーチアドバイザー』サービスでは、この点をとても重視しています。なぜなら、同じテーマでも「どの回答形式で聞いたか」によって、施策の方向性(人事異動・エンゲージメント介入・人材育成投資の優先順位など)が変わってしまうからです。
このコラムでは、
- 複数回答形式(MA: Mark All That Apply)
- 個別強制選択形式(FC: Forced Choice)
の違いと、それによって生じる「最小限化」という行動をわかりやすく解説します。そのうえで、従業員サーベイなど実務の場で、私たちがどのように設計のアドバイスをしているかをご紹介します。
まず用語の整理:MA形式とFC形式とは?
MA形式(複数回答形式)は、1つの設問に対して項目がずらっと並び、「あてはまると思うものにチェックを入れてください」とするタイプです。たとえば「あなたがPCを選ぶときに重視する点をすべて選んでください」という聞き方。チェックボックスを好きなだけ選べます。
FC形式(個別強制選択形式)は、同じ項目リストを並べるのですが、各項目ごとに「はい/いいえ」などを必ず選んでもらいます。つまり1項目ずつ「これは重視する? しない?」と判断させていく形です。
ぱっと見は似ていますが、回答のされ方は大きく変わります。あるWeb調査の検証では、まったく同じ内容を聞いても、MA形式よりFC形式のほうが「選ばれた項目の数」が明らかに多いことが確認されています。たとえば「ノートPCを買うとき何を重視するか」という質問では、FC形式のほうが“重視する”と回答された項目が平均的に多く、MA形式では少なく出る傾向がありました。なぜそんなことが起きるのか。その背景にあるのが「最小限化」という行動です。
“最小限化”とは?
アンケートに答えるには、実はわりと頭を使います。
- 質問の意味を理解する
- 自分の記憶から関連する経験や考えを思い出す
- それが当てはまるか判断する
- 用意された選択肢の中で一番近いものを選ぶ
このステップをきちんと踏むには、一定程度の認知的エネルギーが必要です。そこで、回答者はときどき“省エネモード”に入ります。これが「最小限化」です。
複数の研究結果から、最小限化には段階があることが知られています。
- 弱い最小限化:まじめには答えているが、深く考える前に「まあこのへんでいいかな」と判断を打ち切ってしまう
- 強い最小限化:ほとんど考えずにパターン的に回答してしまう(例:「全部はい」「全部いいえ」「はい・いいえ・はい・いいえ…と機械的に交互に入れる」など)
もちろん、私たちが知りたいのは本音や実態であって、回答の“省エネ具合”ではありません。だからこそ、この最小限化がどこで起きやすいかを理解するのが重要です。
なぜMA形式は“少なく選ばれやすい”のか
MA形式(「あてはまるものをすべて選んでください」)は、回答者が自由にチェックしていきます。一見ラクそうですが、実はここで弱い最小限化が起きやすいと言われています。なぜかというと、MA形式では回答者が以下のような行動をとりやすいからです。
- リストの上のほうだけ見て、ある程度チェックしたら満足してしまい、下のほうまで真剣に検討しない
- 「これも当てはまるけど、まあいいか」と、途中で検討をやめてしまう
つまり、本当は当てはまる項目がまだあるのに、そこまで到達しない/深く確認しないまま回答を終えてしまうことがあります。これが“弱い最小限化”による取りこぼしです。
その結果、
- 本当は「重視している点」はもっと多いはずなのに、少なく報告される
- 本当は「やっている行動」はもっと多いはずなのに、少なく報告される
という“控えめなデータ”が得られてしまいます。実際、ウェブ調査で、インターネット利用行動やPC購入時の重視点を尋ねたところ、FC形式のほうが「該当する」と答えられた選択肢の割合が平均で10〜30ポイント以上高いケースも確認されています。
要するに、MA形式は“ラクに終われる”がゆえに、回答者が自分の本当の行動や重視点をすべて挙げ切らないことがある、ということです。これが「回答形式間の差異」です。そして、こうした差は、単に統計上のブレではなく、回答のしかたそのものに由来するバイアスだと考えられています。
FC形式はなぜ違うのか?
一方でFC形式(1項目ずつ「はい/いいえ」を選ばせる)は、回答者に各項目を必ず検討させます。意識的に1つずつ「これは当てはまる?」「これは当てはまらない?」と判断させるので、項目ごとの情報処理が深くなりやすい、と報告されています。
この「1つずつ考える」プロセスが、弱い最小限化を抑えます。結果として、
- 回答時間はMA形式よりも長くなる
- しかし、より多くの項目が「該当する」と判定されやすい
という傾向が観測されています。
つまりFC形式は、MA形式よりも「ちゃんと考えさせる圧力」が強い。そのぶん、ヒアリングしたい実態(行動の有無、重視点の多様さなど)を拾いやすい、と解釈できます。
調査としてはありがたいのですが、実務ではデメリットもあります。FC形式は回答に手間がかかるので、設問が長すぎると回答離脱(途中でやめられる)リスクも上がります。回答時間が長くなるからです。ここが設計の難しいところです。私たちが現場でやるべきなのは「とにかくFC形式にすればいい」でも「MA形式はダメ」でもなく、どの質問でどちらを採用するべきかを目的別に決めることです。
“最小限化”は雑な回答だけの話ではない
「最小限化」と聞くと、全部いい加減に答える“強い最小限化”を想像しがちです。ですが、実務的にもっと怖いのは“弱い最小限化”です。弱い最小限化は、「まあここまででいいか」と途中で思考を止めるだけなので、ぱっと見は“ちゃんと答えている人”に見えます。異常なパターン(全部同じ、といった極端な回答)にはならないので、集計しても一見きれいなデータに見えます。
でも実は、下位項目や細かい選択肢がまるごと過小評価されているかもしれないのです。この歪みをそのまま意思決定に使うと、「従業員はこの施策をそこまで求めていないらしい」「顧客はここは重視していないらしい」という“誤った控えめ評価”を組織が信じてしまう危険があります。これが、私たちが「回答形式間の差異とその最小限化を軽視しないでください」とお伝えしている理由です。
人事領域だとどう効いてくるのか?
ここからが本題です。MyStoryの『リサーチアドバイザー』サービスは、特に人事・組織開発の現場でこの論点を重視しています。人事領域のサーベイでは、たとえばこんな問いがよく出ます。
- 離職リスクになっている要因はどこか
- 高く評価される人材(ハイパフォーマー)は、どんな環境要因・マネジメント要因で実力を発揮しているのか
- 現場が本当に欲しがっている人事施策・育成施策はなにか
- 異動・配属でハマりやすい環境条件はどれか(いわゆる適材適所のヒント)
問題は、これらが“1つの正解”で説明できる話ではないことです。むしろ「いくつも当てはまる」ケースが普通ですよね。
たとえば離職の予兆。「上司との関係がよくない」「仕事量が多い」「成長感がない」「評価が正当に感じられない」「働き方に柔軟性がない」──本音では複数あてはまることが多いです。
ここでMA形式を安易に使うと、弱い最小限化によって“最初に思いついた1〜2個”だけが選ばれ、ほかの重要な不満が拾われにくくなるリスクがあります。つまり、本当は複合的な離職要因なのに、経営には「結局いちばんの理由はこれらしい」と単純化されて報告されてしまうかもしれないのです。
逆にFC形式で1項目ずつ「これは当てはまりますか?」と聞けば、本人のなかでは“2番手・3番手の不満”も浮かび上がりやすくなります。すると、「残業時間の多さだけじゃなく、配属のミスマッチ感も実は効いている」「評価制度の不透明さも一定の割合で効いている」といった、より具体的な改善ターゲットが見えるようになります。
この違いは、離職対策の打ち手そのものを変えます。
- MA形式のまま弱い最小限化が入り込んだ結果
→ 「とりあえず残業時間を減らそう」といった単発の対策になりがち
- FC形式で複合的な不満構造を拾えた結果
→ 「業務量マネジメントだけでなく、配属ロジックや評価の納得感も改善対象だ」と、組織的な設計改善まで議論できる
MyStoryのピープルアナリティクスでは、離職予測モデル(勤怠データ・行動ログ・意識サーベイを用いた機械学習モデル)と、こうしたサーベイ設計の知見を組み合わせて、「誰が辞めそうか」だけでなく「なぜその人は辞めそうなのか」を部門・職種ごとに可視化します。これは現場のマネジメント改善や、ハイパフォーマーの定着・再現条件の抽出にもつながります。
MyStoryが実際にやっていること(実務の設計アドバイス)
MyStoryの『リサーチアドバイザー』サービスでは、従業員サーベイや会員向けアンケートを設計するとき、次のような観点でフォーマットを提案・修正します。これは単なる「アンケートのお手伝い」ではなく、意思決定に耐えるデータにするための専門支援です。
- どこはMAでよいか/どこはFCにすべきかを分ける
✓“網羅的に拾いたい要因”(離職理由・不満要因など)はFC形式を優先し、取りこぼしを防ぐ
✓回答負荷が高すぎる場合は、項目数を整理したうえでFC形式を当てる
- 順序バイアス(上にある項目が選ばれやすい)をどう抑えるか
✓MA形式では、リストの前半ほど選ばれやすい傾向が観測されることがあります。これは、リスト後半に到達する前に検討を打ち切る“弱い最小限化”の一種と解釈できます。
✓そこで、質問によっては提示順序をランダム化・反転させるなどの設計を行います。
- “強い最小限化”の検知・除外ロジックを用意する
✓たとえば「ほぼ全項目を同じ回答パターンで高速に埋める」など、明らかに内容を読んでいない回答は、分析工程でフラグをつけ、レポーティング前に扱いを検討します。これにより、ノイズに引きずられない集計ができます。
- サーベイの結果を人事施策・組織設計とつなげる
✓“離職リスクが高い層の特徴”や“高評価人材に共通する職場環境”は、単なる平均スコアでは見えません。
✓私たちは、計量経済学(固定効果モデル、操作変数法、切断・打ち切りデータに対応するトービット型/ヘックマン型モデルなど)や機械学習モデルを組み合わせ、要因とアウトカムの関係を丁寧に切り分けてから提案します。これによって「どの部署から手をつけるべきか」「どの条件を守ればハイパフォーマーが活躍しやすいか」を経営・人事に提示できます。
まとめ:アンケートは「聞き方の一文」で結果が変わる
MA形式(複数回答可)はラクに答えられる一方、「とりあえずこれでいいか」と途中で検討を打ち切る“弱い最小限化”が起こりやすく、結果として本当は当てはまる要因が過小に報告されやすいことが知られています。
- FC形式(1項目ずつはい/いいえを聞く)は回答の負荷は上がりますが、各項目をしっかり考えさせるため、より多くの該当要因が拾われやすい、という傾向が確認されています。
- この差は、人事領域では「離職の本当の理由」「ハイパフォーマーが活躍できる環境要因」「従業員が本当に欲しい施策」の見え方を大きく左右します。
MyStoryの『リサーチアドバイザー』サービスは、こうした調査設計・回答品質管理・分析・提言までを一体でサポートします。「アンケートをとって終わり」ではなく、「回答結果を正しく読む前提をつくる」ところから並走するのが、私たちの役割です。
【参考】MyStoryの『リサーチアドバイザー』サービス紹介ページ
『リサーチアドバイザー』サービスへ移動